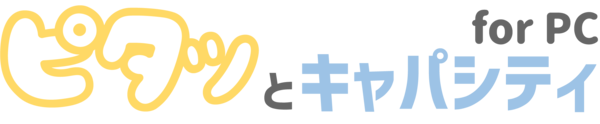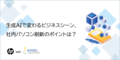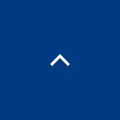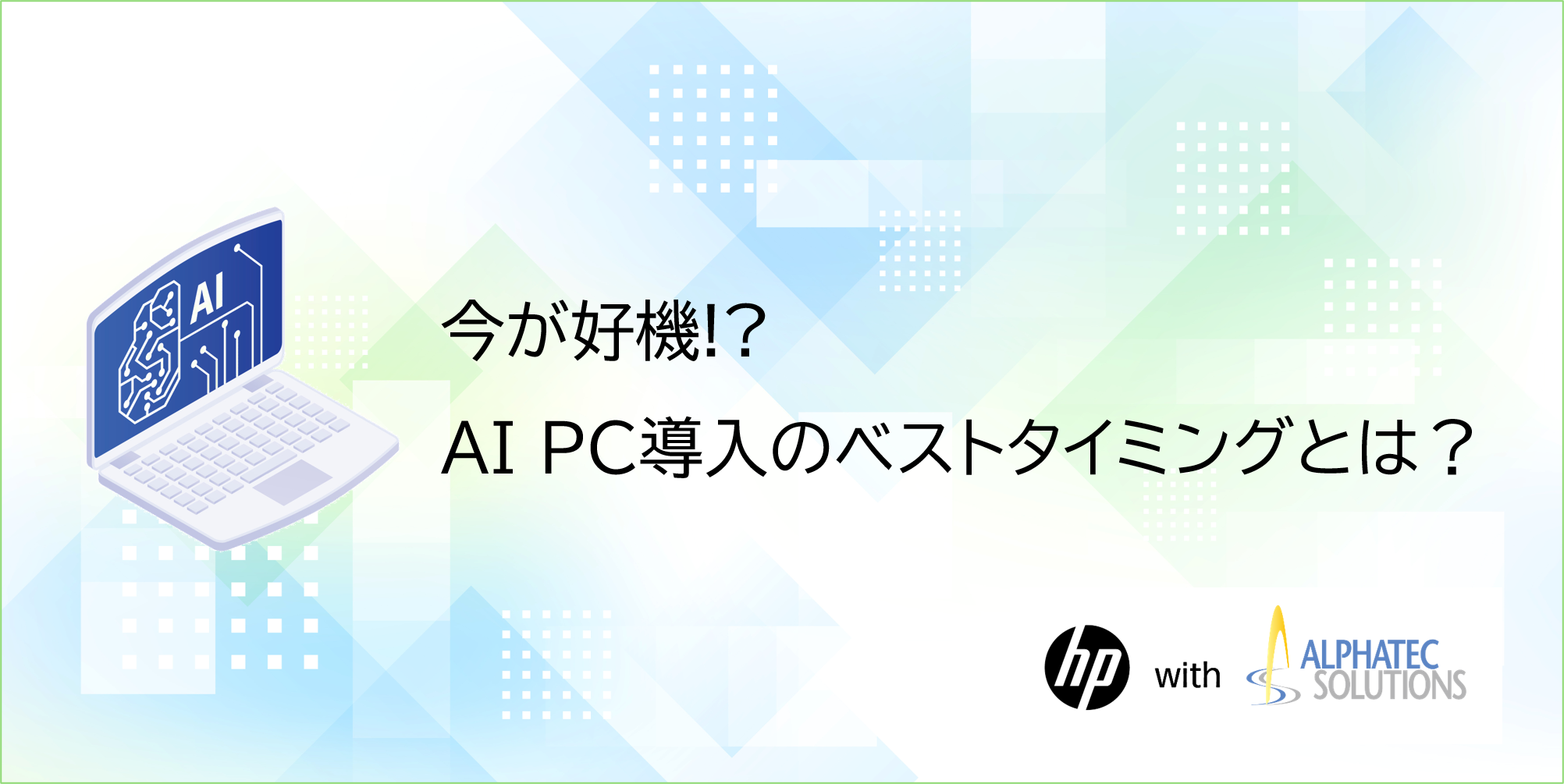
今が好機!? AI PC導入のベストタイミングとは?
目次[非表示]
マイクロソフトによるWindows 10のサポート終了が10月14日に迫っています。サポート期限を過ぎると、Windows Updateを介したWindows 10の無料ソフトウェア更新プログラム、セキュリティ更新プログラム、テクニカルサポートは提供されなくなります。そのまま使い続けることは、①セキュリティの不安、②機器やソフトウェアの互換性問題、③運用コストの増加――といったリスクにつながります。それぞれの問題について、現状をアップデートしていきましょう。
ランサムウェアの被害につながるパスワード攻撃が急増
まずセキュリティのリスクについて、過去のブログ(Windows 10のサポート切れまで1年、移行準備のポイントは?|連載第1回)で特に攻撃規模や被害額の上昇が著しいランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の脅威について取り上げました。社内にランサムウェアが侵入してファイルサーバーが感染すると、アクセス不能になったりファイルが暗号化されたりして、利用できなくなります。この状態から正常な状態に戻すために身代金を要求され、金銭的被害が生じるケースも多々発生しています。
この攻撃で侵入の足掛かりとして多用されるのが、パスワードを不正に取得・推測・利用してシステムやアカウントに侵入する手法です。マイクロソフトが2024年に公開した「Digital Defense Report 2024」の中では、1日に78兆件以上のセキュリティ信号を処理したところ、毎秒7000件以上のパスワード攻撃を検知したとの報告があります。このパスワード攻撃には、考えられるすべてのパターンを専用ソフトウェアで試す手法や、フィッシング詐欺などによって過去に漏えいしたリストを試す手法があります。

Windows 10では全機能を使えない?ソフトウェアのWindow 11対応も進展
機器やソフトウェアの互換性問題も、2021年にリリースしたWindows 11の普及が進むにつれて懸念が高まってきました。ソフトウェアベンダーはWindows 11のユーザーが増えてくると、Windows 11の新しいUI(ユーザーインターフェース)や機能、パフォーマンスを前提とした製品開発にシフトしていく傾向があります。
そうなるとWindows 10の環境ではソフトウェアの全機能を使えなくなったり、動作が不安定になったりするケースが出てきます。具体的には、Windows 11で強化したハードウェア・セキュリティ機能や仮想化技術に対応するソフトウェアで、こうした問題が生じやすいとされています。逆に、Windows 10対応アプリケーションのうちの99.7%以上はWindows 11でも正常に動作するとマイクロソフトは発表しています。このため、Windows 11にアップグレードするほうが、互換性の問題は生じにくいと言えるでしょう。
最後が、パソコンの運用コストが増加するリスクの問題です。マイクロソフトは、Windows 11への移行が間に合わないユーザーを対象に、2025年10月14日以降も最低限のセキュリティ対策を3年間提供するESU(拡張セキュリティアップデート)プログラムを提供します。ただし、ESUの利用には1台当たり年間で61ドル(1年ごとに2倍に増額)のライセンス費用がかかる見通しです。
加えて、ESUではセキュリティアップデートの更新は受けられますが、アプリケーションの互換性やドライバーのアップデートは担保されません。つまり、運用コストが上がるうえに、セキュリティリスクも高まることになりますので、社内システムのコストパフォーマンスは大幅に低下することとなります。
これらのリスクを回避し業務効率を安全に向上させる観点から、Windows 10のサポート終了のタイミングでのWindows 11へのアップグレードは、やはり避けては通れない道と言えます。

パスワード攻撃に有効なハードウェア・セキュリティ機能
Windows 10のサポート切れとなる10月まであと半年あります。ですが、OS移行に向けて導入するAIアプリケーションやパソコンの仕様を検討し、さらに購入、納品、キッティングに要する期間を考えれば、この春から導入検討に着手するのがお勧めです。その理由の1つは、Windows 11で強化したハードウェア・セキュリティの必要性が高まっていることです。
ランサムウェアの足掛かりとされるパスワード攻撃が爆発的に増えていることは前述しましたが、Windows 11で標準対応になったセキュリティ・プロセッサー「TPM(Trusted Platform Module)2.0」と「パスキー」にはパスワード攻撃の被害を防ぐ機能があります。
TPMには、IDを強固に守る「Windows Hello」によるログインで使われる認証データ(生体認証、PINなど)や、保存データの暗号化処理で利用する鍵情報、デバイス証明書の署名データなどが格納されます。攻撃者はこれらのTPMの格納情報にアクセスできないと、Windows 11のサインインや記憶ディスクの暗号化解除はできません。また、パスキーはWindows 10で搭載した「Windows Hello」を進化・統合させた認証機能で、生体認証などを使うことにより従来のパスワードを使わないログインが可能です。これらの機能がパスワード攻撃の対策に役立ちます。

飛躍的にNPU高速化が進んだ現行モデルの買い時は?
今がOS移行の最適なタイミングと考えるもう1つの理由は、AIアプリケーションの利用に最適な「Copilot+ PC」のプロセッサーに搭載されているNPUの実行速度が飛躍的に高まったことです。Copilot+ PCは、NPUの演算処理速度が40TOPS(Tera Operations Per Second)以上、RAMが16GB以上、ストレージは256GB以上と規定されています。40TOPS以上のNPUを搭載したパソコンは2023年以前に存在せず、過去のハードウェアが切り捨てられたという点で非常に対応が難しい仕様と言えます。
この1年のプロセッサーの進化を振り返ると、Intelが2023年末に提供開始した「Meteor Lake」の11TOPSから、2024年後半に登場した「Lunar Lake」は最大48TOPSと約4倍になりました。AMDも同様に、昨年登場の「Ryzen AI 300」は50TOPSを達成し、前モデルの「Hawk Point」の16TOPSから約3倍に飛躍しました。半導体プロセスの微細化やAI推論処理に特化したアーキテクチャの最適化などで実現した高速化により、動画のリアルタイム処理を含む高度なAIアプリケーションの利用が可能になりました。
特に、当社で取り扱うCopilot+ PCの「HP EliteBook X G1a 14 AI PC 」は、AMDとHPが共同でAMD製「Ryzen AI300」プロセッサーのNPUをチューニングしたことにより、55TOPSの処理速度を実現しています。これは発売されているパソコンの中で最高クラスのスペックになります。一方で、プロセッサーがIntel製Core Ultra 200Vシリーズになる「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」はNPUが47TOPSになりますが、重量が1.19kgとG1aより約0.3kg軽量などの特徴があります。
Intelは今後、NPU速度をさらに高めた「Panther Lake」を2025年後半以降に発表する見通しです。そのプロセッサーを搭載した次世代モデルを待つべきかどうかは判断が難しいところですが、次世代モデル登場前の春から夏にかけて現行モデルの価格が下がる可能性や、Windows 10のサポートが切れる前に余裕を持って移行を進めることを考えれば、この春に導入することは理想的なタイミングと言えるのではないでしょうか。

HP EliteBook X G1a 14 AI PC
スムーズな大量移行にはクローニングが有効
Windows 11パソコンの導入を決断したら、早急に導入までの段取りを検討する必要があります。当社のパソコン管理代行サービス「ピタッとキャパシティ for PC」では、導入機種の選定から、導入機種が決まった後のスムーズな移行までしっかりサポートします。
パソコンの移行に当たっては、既存のデータをバックアップした後で、新機種へのOS・アプリケーションのインストールや社内ネットワークへの接続設定などが必要になります。これらを手作業で実施すると、1台当たり2~3時間はかかるのが一般的です。導入する台数が数十台を超えると設定ミスが発生する可能性も高まります。
こうした作業を正確かつ効率化しながら実行するには、過去に詳しく説明した、マスターからクライアントへのパソコン複製(クローニング)が有効です(参考ブログ:Windows 11パソコンへの大量移行を効率化する方法は?|連載第5回)。それらの作業を代行する「ピタッとキャパシティ for PC」ならば、OS移行作業でIT部門にかかる負担を大幅に軽減できます。
さらに導入後の運用管理やPC保守、さらには運用終了後の対応などパソコンのライフサイクル管理も「ピタッとキャパシティ for PC」で対応できます。IT部門および実際にパソコンを利用する社員の双方にとって、効率的なパソコンの運用管理を実現できるサービスにご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
記載の企業名、製品名は各社の商標または登録商標です。ブログ記事は掲載時点(2025年4月)における情報をもとに執筆しており、著者の意見や経験に基づく内容を含んでいます。掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。