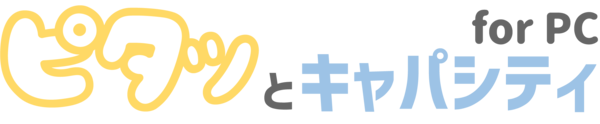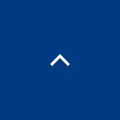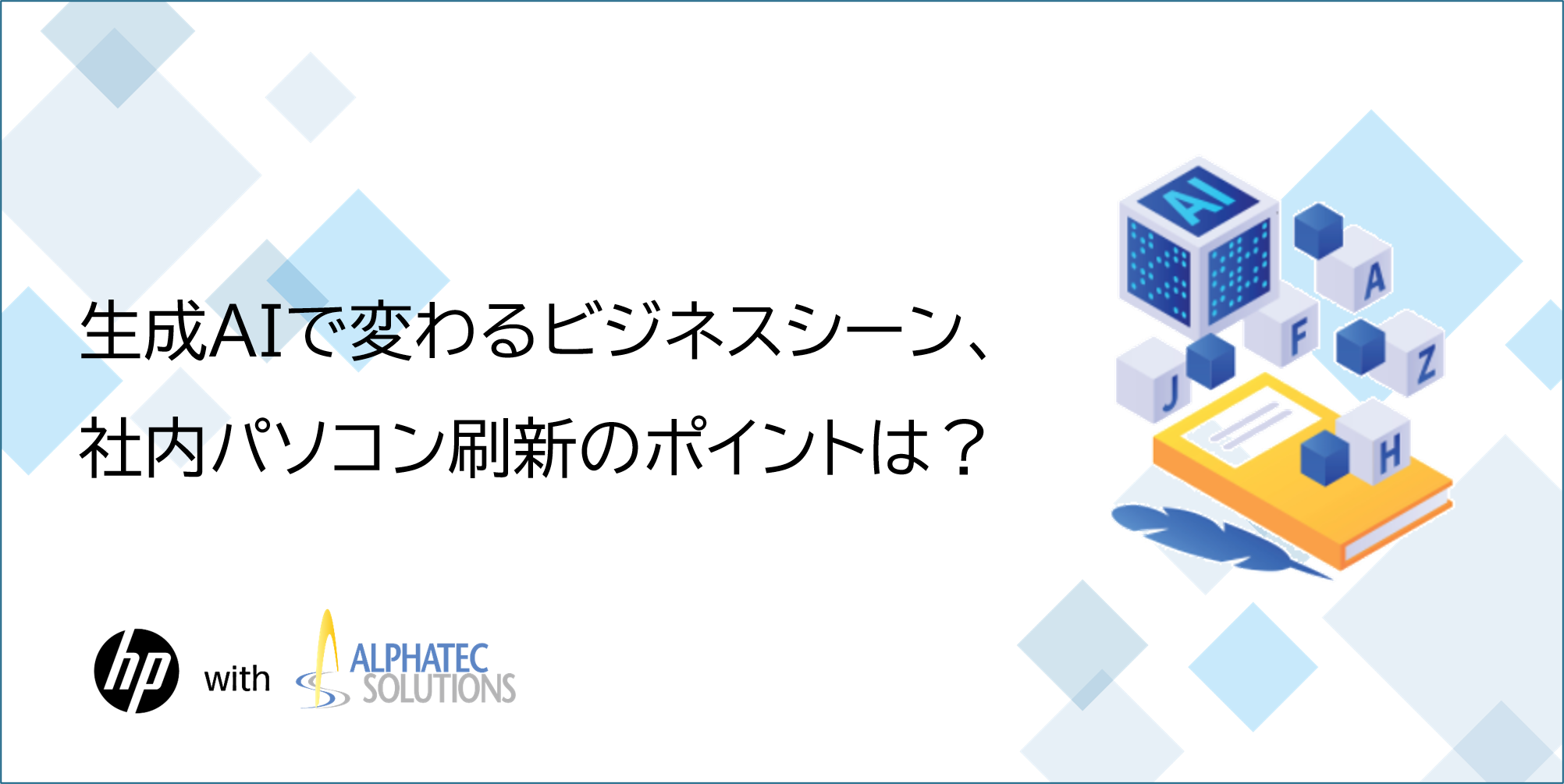
生成AIで変わるビジネスシーン、社内パソコン刷新のポイントは?
目次[非表示]
NPU搭載のAI PC、Copilot+ PCは40TOPS超
Windows 11の目玉であるAIアシスタント機能群「Copilot in Windows」を快適に利用できるパソコンとして、過去のブログ(AI機能フル活用に向け、Windows 11のハードウェアの強化が進展|連載第4回)で「AI PC」や「Copilot+ PC」の動向について紹介しました。AI PCは生成AIの処理能力を高めたWindowsパソコンの総称で、IntelとMicrosoftが中心となって2023年に提唱したものです。定義はそれほど厳密ではありませんが、生成AIの推論処理を高速に実行できるNPU(Neural Processing Unit)を内蔵するプロセッサーの搭載を求めています。
一方で2024年に登場したCopilot+ PCは、NPUの演算処理速度は40TOPS(Tera Operations Per Second)以上、RAMは16ギガバイト(GB)以上、ストレージは256GB以上と明確に規定しています。これはMicrosoftがCopilot in Windowsに追加した高機能なAIアプリケーションを快適に動作させるパソコンを明確にする必要があったからです。キーボードにAI機能を簡単に起動できる「Copilotキー」を備えることは、AI PCとCopilot+ PCのどちらにも求められています。
つまり、AI PCのほうが広義な呼称で、Copilot+ PCはより厳密で狭義な呼称と言えます。最近では、パソコンメーカーが多くのCopilot+ PC対応モデルを展開していることもあり、Copilot+ PCという呼称の認知度が高まっているかもしれませんが、プロセッサーメーカーはAI PC向けとPRする傾向があるようです。
AI PCが登場した2023年から、Intel、Qualcomm、AMDがNPU内蔵プロセッサーを提供しています。当初はNPUの処理速度が10TOPS程度でしたが、2024年には45~50TOPSとCopilot+ PCの基準を満たすプロセッサーが登場しました。

生成AIアプリケーションを「より快適」「より安全」に
NPUを搭載したAI PCでなければ、ユーザーは生成AIアプリケーションを使用できないのでしょうか。こうした疑問をもつ人が多いようです。実際には、多くのユーザーがAIチャット「ChatGPT」を利用しているように、既存のパソコンで使える生成AIアプリもあります。ただし、AI PCやCopilot+ PCでNPU対応のAIアプリケーションを使えば、より快適かつ安全にAIデータ処理を実現できるのです。
生成AIの演算は、主にクラウド側で行なわれるデータの「学習」(ラーニング)の処理と、その学習を基に「推論」を行って新たな情報を生成する処理の2つの部分に大きく分かれます。後者の推論も従来は主にクラウド側で処理するのが一般的でしたが、NPUを搭載し推論をパソコン側で処理するアプリケーションが増えてきました。NPUの高速化により推論処理が短時間で済むので、消費電力を抑えてノートパソコンのバッテリー駆動時間を長くできます。
例えば、当社で取り扱うCopilot+ PCの「HP EliteBook X G1a 14 AI PC」は、55TOPSのNPUを内蔵するAMD製「Ryzen AI300」プロセッサーを搭載し、8~13時間と1日中使用できるバッテリー駆動時間を実現しています。また、パソコン内でAIを処理できるので、推論に使うデータをクラウド環境に出さずに済むため、セキュリティを高められるメリットもあります。その他にも、HPのCopilot+ PCのラインナップとして「インテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2)」搭載の「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」も取り扱っています。
既存パソコンで使えるAIアプリケーションとしては、先に挙げたChatGPTのほか、Googleの「Bard」や「翻訳」など、主にクラウド側でAI処理する設計になっているものがあります。また、ゲーミング用などの高性能なCPUやGPUを搭載するパソコンであれば、NPU非搭載機でもある程度のAI処理が可能です。この場合は、検索結果などの要約や文章作成、画像中の文字認識などCopilot in Windowsの初期機能や軽量版の生成AIツール、機械学習モデルなどは動作する可能性は高いでしょう。また、Microsoft OfficeやAdobe PhotoshopのAI支援機能のように、パソコンのスペックに合わせて動作を最適化するアプリケーションも使用できます。
一方で、2024年にCopilot in Windowsに追加した高機能なAIアプリケーションは、Copilot+ PCでなければ十分に動作しない恐れがあります。具体的には、動画再生時に音声翻訳文字をリアルタイム表示する「ライブキャプション」や、Web会議中に参加者のカメラ目線を維持したり背景の人の動きにボカシを入れたりする「Windows Studio エフェクト」などです。このため、Windows 11にアップグレードする際には、導入するAIアプリケーションを想定したうえで、パソコンの仕様を決めるのがお勧めです。

HP EliteBook X G1a 14 AI PC
営業・総務・企画の各部門で立ち上がるAI活用事例
続いて、企業でAI PCを導入したことにより業務効率化などのメリットをもたらした事例を、部署別に紹介します。
まず営業部門で多い生成AIの活用例は、顧客の購買履歴や問い合わせデータをセキュアに分析して、ターゲットや提案内容を即座に生成する用途です。実際に生成AIを活用して営業活動を効率化し、受注率を平均5%向上させている企業もあります。
また、商談の会話内容をリアルタイムでテキスト化し、その要点をCRMに即座に反映させ、フォローアップを迅速化する活用例も広がっています。ローカル環境で高速処理できるAI PCなら、営業担当者が移動中でも迅速な顧客対応を実現し、商談成功率の向上などの効果が期待できます。
続いて総務・経理部門での活用例です。人手不足に悩むケースでは社員からの経費精算や休暇申請などの定型的な問い合わせに生成AIで自動対応し、総務・経理部門の社員は規程改定などの戦略的業務に活用する例が多いようです。自社開発のAIチャットボットを活用して社内問い合わせ対応を自動化し、電話による問い合わせ件数を3カ月で1000件削減することに成功した大手IT企業もあります。さらに、過去の契約書や規定の文書をAIが解析して、検索性を高めるインデックスを自動作成し、総務・経理部門の社員が文書を探す手間を削減する例も増えています。
そして企画部門では、新しい製品やサービスの企画案、プレゼン資料を短期間で作成する目的で、市場データやトレンドなどを基に生成AIが自動生成しています。マーケットや売り上げなど過去のデータから、将来予測をシミュレーションする用途も多いです。AI PCを使えば、機密データをローカル環境に保存したうえで高速処理できるため、業務を安全かつスピーディーに遂行できるようになります。新規作成した広告と既存広告を生成AIで比較し、より効果の高い広告を顧客に提案する企業も出てきました。

AI活用にマッチするOS切り替え計画をサポート
このように、ビジネスシーンでの生成AI活用はごく一般的な流れになりつつあります。そうした状況でWindows 11へのOS切り替えなどで全社のパソコンを刷新する際には、AI活用による業務効率化を念頭に置いて、導入計画から検討することが会社の競争力を向上させるポイントとなります。現在の業務フローを整理して、導入するAIアプリケーションを決定し、快適に動作する仕様のパソコンを選ぶといった段取りが必要になります。
新しいパソコンの導入計画は自社で検討するのが理想的ですが、IT人材の不足などにより難しい場合は、当社が提供しているパソコン管理代行サービス「ピタッとキャパシティ for PC」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。これは当社が15年間蓄積したPCライフサイクルマネジメントのサービスで、①計画、②調達、③導入、④運用管理、⑤PC保守、⑥リユース――といった6フェーズに体系化して、導入から運用管理までをサポートします。サービス内容の詳細は、改めてブログで紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてください。
記載の企業名、製品名は各社の商標または登録商標です。ブログ記事は掲載時点(2025年4月)における情報をもとに執筆しており、著者の意見や経験に基づく内容を含んでいます。掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。