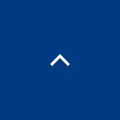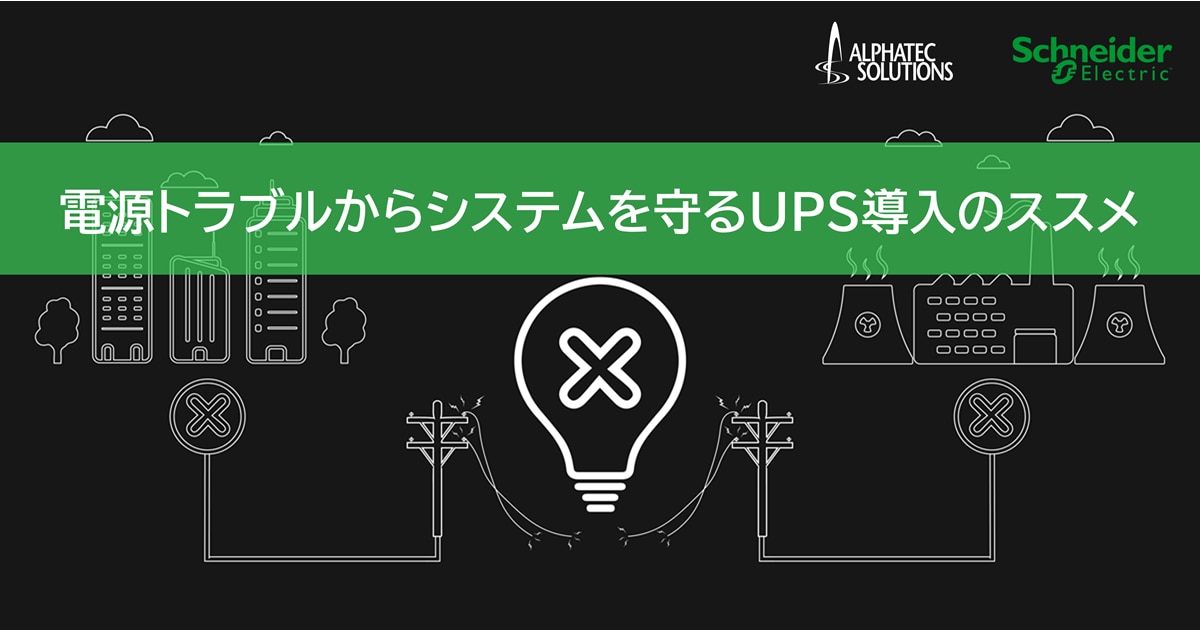
電源トラブルからシステムを守るUPS導入のススメ
企業におけるITシステムの利用拡大に伴って、IT関連機器の電力消費量が爆発的に増加しています。総務省の情報通信白書(令和4年版)では、2030年には現在と比べ、年間使用電力量が倍近くに増加するという予測が記載されています。
アプリケーションソフトと保存したデータを1台のノートパソコンだけで利用する旧来のケースでは、停電の際にも内蔵バッテリーで業務を継続できました。しかし、今ではサーバーや社内外のデータセンター、クラウドサービス上などにデータを保存するシステム形態が一般的になっています。
このため、社内のパソコンやサーバーだけでなく、社内外のシステムと連携するためのネットワーク機器やセキュリティ関連機器といった多様な機器へ電源を供給し続けることが、ビジネスの継続性を確保するためには重要となります。そこで注目を集めているのが、停電時でも社内システムへ一定時間電源供給可能な「無停電電源装置」(UPS)です。
自然災害の増加などで停電リスクが増加
企業内システムの変化という内的要因に加えて、雷、台風、地震などの自然災害の増加や、猛暑といった外的要因による停電のリスクも高まっています。エアコン需要の急増による電力の切迫だけでなく、気象庁のデータによると2024年7月の東京では過去7年の平均と比べて8.5倍の落雷が発生しました。2025年7月には、宮古島で雷雲の発達による一時的な全島停電が発生しています。東日本大震災の時の計画停電は記憶に新しいですし、実施にこそ至りませんでしたが記録的な暑さだった2023年にも東京電力が計画停電を実施する可能性を公表しました。
日本列島における地震活動も相変わらず活発な状況です。気象庁の発表によると震度1以上の有感地震が2024年は約3700回と、過去の統計の上位10%に入る多さですし、つい最近もトカラ列島では1カ月で2000回を超える群発地震が発生しています。2024年8月に宮崎県で発生した震度6弱の地震を受けて、気象庁が南海トラフ地震の可能性を公表し、情報提供を継続しています。
珍しい話題としては、2022年に福島県郡山市の変電所において蛇の侵入が原因でショートが発生し、短時間ですが約9800戸が停電となった事件もありました。このように、多様な停電リスクが混在する環境のなかで、UPSを使った対策があらゆる企業に求められています。

クラウドの利用拡大で停電対策が不可欠に
以前より、停止した際に社会的に重大な影響を及ぼす危険性がある金融や医療などの業界では、データ保護やシステム稼動に関する規制やコンプライアンスに対応するために、安定した電源供給をはじめとするミッションクリティカルなシステム運用が求められていました。ところが昨今では、そうした話はもはや特定の業界だけではなくなってきたのです。
そのため、例えばデータセンターやクラウドサービスなどのIT業界に加えて、製造業、小売業、物流業、サービス業などの多様な業種において、大企業を中心にUPSの導入が進んできました。最近では低価格なUPS製品が増えてきたこともあり、中小企業での導入も加速しています。その結果、国内のUPS市場(出荷額)は2022年度の約868億円から、2025年度までに931億円へと拡大すると予測されています。
※出典:UPS市場に関する調査、矢野経済研究所、2023年

当ブログでは、2025年10月にマイクロソフトのサポートが終了するWindows 10からWindows 11に円滑に移行するためのノウハウを6回の連載でお伝えしました。特に大量のパソコンのOS、アプリケーション、設定などを更新する際には、手作業だとミスが起こる可能性が高まります。このため、パソコンのセットアップに「Windows Autopilot」サービスを活用してネットワーク経由で自動化すると、業務効率化に有効であることもお知らせしました。
※参考:【連載】Windows 11パソコンへの大量移行を効率化する方法は?|第5回
こうしたOS移行やソフトウェアの更新中にも停電が起こる危険性はもちろんあります。そのような状況になった場合、ネットワーク機器の停電対策を怠ると、システム障害やデータ破損など、業務に支障をきたす事態を引き起こす恐れがあります。パソコンにも悪影響が出る可能性もあるので、ネットワーク機器の停電対策は事業継続性の観点から非常に重要です。
高い信頼性を武器にシェアを広げるシュナイダーエレクトリックのUPS
数あるUPSのなかで、当社がお勧めしているのは仏シュナイダーエレクトリック社の製品です。同社は40年以上の電源保護ソリューションの提供実績を持ち、ミッションクリティカルな環境での利用に適した高い信頼性に定評があります。年間販売台数が1位の製品に贈られる「BCN AWARD」のUPS部門において、10年連続で1位(通算16回)を獲得しています。2024年は日本市場でのシェアが約50%(※)に達しました。
※BCN AWARD調べによる
シュナイダーエレクトリックは幅広い用途向けに製品群を用意しています。サーバールームやデータセンターでの利用を対象とする「SRTシリーズ」、中小規模システム向けの「SMT/SMXシリーズ」などがラインナップされています。
SRTシリーズでは、停電時の切り替えの際に電源の瞬断がまったく発生しない「常時インバーター方式」を採用して、ミッションクリティカルな用途にも対応します。またSMT/SMXシリーズでは、停電時の電源切り替え時間が5~10ミリ秒の「ラインインタラクティブ方式」を採用して、中小規模のオフィスでも導入しやすい価格に設定されています。ミッションクリティカルな用途以外であれば十分に対応できるスペックです。どちらも導入規模に応じた多様な出力容量やバックアップ時間の製品群から選択できます。

社内LANやIPカメラもUPSで停電対策
シュナイダーエレクトリックのUPSを採用した事例について大企業を中心に紹介しましょう。
まず全国に数十拠点を持つ、あるグローバル商社では社内のコアスイッチなどの基幹系システム向けのネットワークにUPSを導入していましたが、オフィスフロアなどに設置する末端のスイッチにはUPSを導入していませんでした。このため、停電時にサーバー間の通信については電源保護がされていたものの、サーバーとパソコンの間の通信は保護されていませんでした。こうした状況下の2016年に雷による停電が発生し、オンラインシステムを使った業務などが継続できなくなり、ビジネスに大きな影響が出ました。このトラブルがきっかけとなってUPSを導入し、今では安定した業務継続体制を構築しています。
また、全国に数百拠点を持つ、ある大手運送会社では全店舗に導入した監視用IPカメラの更改を2016年に控え、停電時でも録画監視を継続できる体制への切り替えを目指していました。とは言え、カメラごとにUPSを接続するのは、コストや設置スペースの問題から困難でした。そこで、LANケーブルを通じて電源供給できるPoE(Power over Ethernet)方式に対応するIPカメラとイーサネットハブを導入し、そのハブにUPSを接続する形態を採用しました。これにより、ハブの電源を数時間バックアップし、さらにIPカメラを雷サージ(雷によって発生する瞬間的な高電圧・過電流)から保護することが可能になりました。
このほかにも、中小企業がSOHO向けのNASやパソコンの停電対策として、同社のUPSを採用するケースも増えています。突然の停電だけでなく、電気設備の点検でブレーカーを落とす際にもUPSが導入されていれば安心です。停電時にはUPSから接続機器を自動シャットダウンしてデータを保護する機能もあり、情報システム担当者の負担を軽減してくれます。
次回のブログ『自社システムにマッチするUPS製品の選び方は?』では、このシュナイダーエレクトリックのUPSの選び方や、情報システム担当者が運用時に重宝する機能を掘り下げてお伝えします。